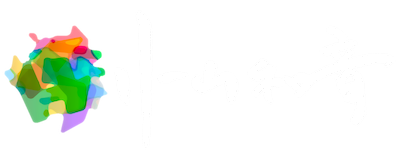日本の音楽教育の問題を解決する特別授業を実施できます
更新 2026年1月5日
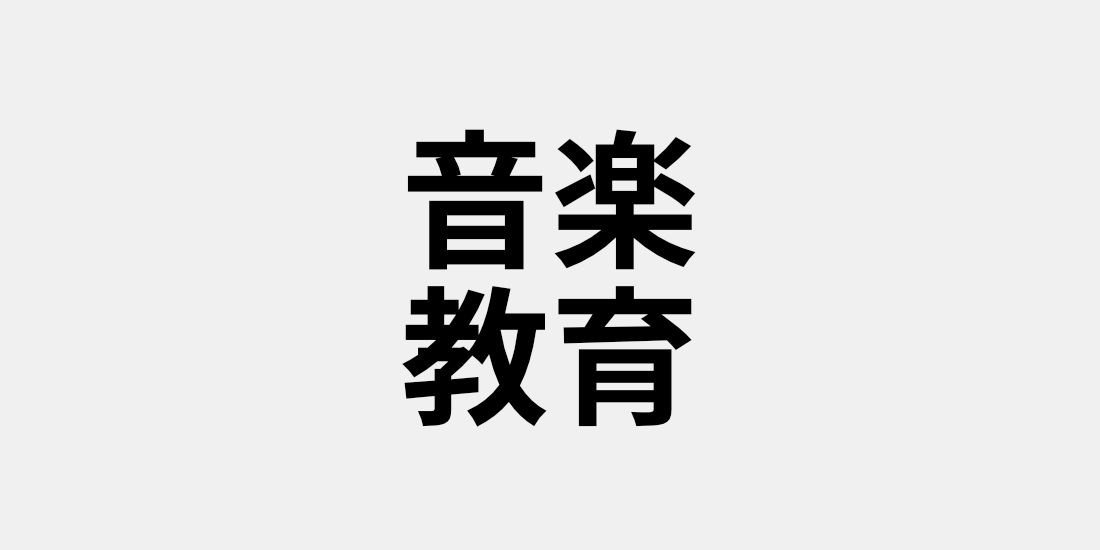
日本の音楽教育は何のために行われていて、その教育を受けることでその目的を本当に達成できるのか、日本の音楽教育にはどのような問題があるのか、そしてその解決策をまとめました。
もくじ
日本の「音楽教育」の目的
日本では幼稚園から高校まで多くの学校に音楽の授業がありますが、その方針を定めている文部科学省の学習指導要領上には以下のような目的が設定されています(幼稚園〜高校までの各内容を要約してあります)1234。
B 音楽によって生活を豊かなものにする
C 表現する能力を高めてその楽しさに気づく
D 鑑賞する能力や感性を育む
日本の音楽教育の問題(矛盾)点
では、こどもには音楽の授業を受けさせていれば、音楽を好きになり、生活が豊かになり、表現する能力がつき、鑑賞する能力や感性が豊かになるのでしょうか?
筆者としては慎重に考えたい点が3つあります。
(1)音楽が「教えられ」ている
まず、音楽の授業そのものが「こどもは何も持っていない」という前提で、音楽を一方通行で「教える」仕組みになっている点です。
そもそも「音楽」というものがいつ生まれ、なぜ存在するのかが不明であるにもかかわらず、人類が生まれた数百万年の中のたった数千年の間で「音楽」とされてきたものだけが音楽のすべてであるかのように(わかったかのように)教えられているというのが現代の音楽教育です。
つまりこれは音楽の本質やこどもが本来持っていたはずの「音楽」については目もくれず、過去数千年というごく一瞬の期間に人類(しかもほとんどがヨーロッパという限られた地域をルーツとする限られた人間)が発展させた音楽のかたちを「正解」や「ゴール」として、私たちをそこに当てはめよう・順応させようとしているプログラムだということです。
一方通行で「教えられる」のが当たり前になり、「模範的な」「ばらつきのない」音楽の感覚に塗り替えられていくことで、こどもが本来持っていた音楽の感覚は徐々に失われていきます。
これは幼少期から音楽学校にわたる筆者自身の体験から実証できるのですが、もともと持っていた感覚はいったん他の感覚に塗り替えられてしまうと取り戻すのがとても難しく、場合によっては一生失われてしまうこともありえます。
Cの表現する能力を伸ばすには、もっと安全で効率のよい方法がありそうです。
(2)評価・分類が行われている
次に、音楽の世界に「優劣」「正解・不正解」「お手本」という考え方を持ち込んでいるという点です。
私たちは生き物ですので、音を出せば誰でもゆらぎや不均一さが生まれますし、そこに個性が表れます。
ところが音楽の授業では「ちゃんとハーモニーをつくりましょう」「ちゃんとリズムを刻みましょう」といって構成音や時間軸上のゆらぎや不均一さを「間違い」や「技術不足」としたり、意図された弾き方・鳴らし方にそぐわない楽器の扱い方を「間違い」や「邪道」として評価をしがちです。
また、クラシックの「名曲」とされている演奏や、そういった演奏を再現するのが得意であったり時間軸上のゆらぎが少ないこどもを「お手本」として他のこどもに聴かせる、といったことも行われています。
これは、出す音にゆらぎがない・均一なほど「良い」あるいは「上手い」、バッハやモーツァルトなど過去の人間やヨーロッパやアフリカなどがルーツの音楽を「正しい」「お手本」「常識」とすることで、間接的に現代の日本のこどもがもともと持っていた音楽の感覚を否定しているということでもあります。
そして「正しいもの」や「お手本」に近いほど評価が高くなり、それが点数として表されますが、これはたまたまそのこどもの表現が過去数千年の間に存在したごく一部の表現に近い、あるいはその再現が得意というだけのことです。
ここで考えられる問題点は、こどもの音楽が教師に認めてもらえなかったり、達成が困難なお手本を提示されることで、音楽に距離を感じるようになる可能性があること、それによって表現したいという気持ちや自信を失ったり、こども自身の個性や人それぞれの違いを認めづらくなる可能性があるということです。
この状態でAの音や音楽への興味関心を養い、音楽を愛好する心情を育てるという目的を果たすことは難しく、Cの表現する能力を高めるどころか抑制してしまう危険性をはらんでいます。
(3)「完成された」音楽を前提にしている
もう一つは、ピアノやギターのように「正しい」鳴らし方が決まっている「完成された」楽器や、五線譜・コードネームのような「正しい」書き方・読み方がある「完成された」楽譜や音楽理論が前提とされている点です。
音楽教育を受けるとき、楽器を選ぶことができるとしても選択肢にあるのはピアノやギター、リコーダーのように他人が完成させた楽器だけで、さらにそれは完成された楽譜(ヨーロッパ式の五線譜)や音楽理論(ヨーロッパ式の12平均律)がベースとなっていて、自分たちでつくる・組み合わせるということが想定されていません。
そのような楽器や楽譜を使いたいという明確な意思があるのならともかく、「何もわからない」「何でもいい」というこどもに、特に理由もなくピアノやギターという完成された道具や完成された楽譜・音楽理論を提示するということは、こどもの創造力を制限している(創造性を発揮するチャンスを奪っている)ということでもあります。
Cの表現する能力を追求するならば、もっと効率的な方法がありそうです。実際、筆者のプログラムでは、完成された楽器や楽譜がなくとも「音楽」を楽しめることが証明されているし、世界中の音楽家もそれを証明しています。
音楽教室(習い事)や音楽学校でも同じ
筆者は日本の幼稚園〜高校に加えて国内外の音楽幼稚園・音楽教室・音楽学校・基礎学校などさまざまな音楽教育の現場を体験してきましたが、幼稚園〜高校以外で音楽を教えるところ(音楽教室や音楽学校)は、幼稚園〜高校の音楽の授業と同じ問題を抱えています。
つまり日本で「音楽を教えるところ」においては、基本的に評価・分類は行われ、音楽は一方通行で教えられ、完成された音楽が前提とされています。
筆者からの提案:『音楽を創る』
私からはこのような提案ができます。
「音楽を創る」は音楽の知識・経験・スキルを前提とせずにゼロからオリジナルの楽器や楽譜をデザインし、それらを使って即興演奏や作曲をするプログラムです。2012年からワークショップとして日本・ニュージーランド・オランダで多数開催し、現在ではそれらの経験をもとに学校の授業の監修も行っています。詳しくはこちら。
「音楽を創る」の特徴
「音楽を創る」には3つの特徴があり、これらを原則としてプログラムが進められます。
(1)教えない

「音楽を創る」では、「こどもは何も持っていないから教えてあげる」という上から目線ではなく、「すべてのこどもはすでに表現できる何かを持っており、それをいかに傷つけずに引き出すか」という姿勢で、敬意を持ってこどもと接します。
こどもの感覚や表現を守りながら引き出すため、私から「音楽を教える」のではなく、自分で表現するための手段やコツといった「参考情報」をこどもに提示しつつ、こどもが自分たちの力で表現するためのお手伝いをします。そのため私は「教師」や「先生」ではなく「こどもの仲間」「ファシリテーター」「進行役」という位置付けです。
どのような素材を組み合わせた道具をどのように鳴らすのか、どのように音楽を記すのか、どのような音を使うのかなど、あらゆる判断をこども自身に委ねます。
裏を返せば、こどもから「こういう音を出す方法はあるか」「友達にこういうことを言われたがどう思うか」「こういう作品を作りたいが何から始めたらいいかわからない」といった質問・相談が押し寄せるということなのですが、そこでは教科書に書かれているような既存の音楽の枠組みを超えた音楽そのものに対する広い視野、音響に関する知見などが求められます。

また、ファシリテーター(進行役)はプログラムを進行するうえで可能な限り自分の主観を排除し、こどもたちの間で発生しうる主観のコントロール(他人の意見や表現を否定しないように徹底させるなど)も行います。
典型的な音楽教育では誰が見ても変わらない事実(客観)と自分の表現やアウトプット(主観)を混同しがちですが、これを分けて考えることで個性や人それぞれの違い(音楽における多様性)が認めやすくなり、こども自身の表現や考え方に自信や価値が生まれます。
これによりCの表現する能力を養うだけでなく、こどもが他のこどもの表現や発想を観察することからDの鑑賞する能力や感性を育むことにもつながります。
(2)評価しない

「音楽を創る」では、正解・間違い・上手い・下手・お手本・才能というような評価や分類は一切行われず、「試験」や「成績」も存在しません。
こどもの表現や考え方に対しては、その内容がどうであってもまずは「なるほど」というようなニュートラルな(肯定でも否定でもない)言葉遣いを徹底し、教師の主観を可能な限り排除します。
これは実際こどもの表現を前にしてみるととても難易度の高いコミュニケーションですが、経験とトレーニングを積み、「もっとこの子のことを知りたい」「もっとこの子から教わりたい」という関心や謙った姿勢を忘れなければ、決して不可能ではありません。

評価や分類が行われないことで、「正解やお手本は存在しないのだから、自分で考えるしかない」と表現を促すことにつながり、そしてここでも「自分や他人ひとりひとりの個性・表現それぞれに価値がある」ということを認めやすくなります。
典型的な音楽教育では評価が行われることで潜在的な上下関係(上手い・下手・良い・悪いなど)が生まれやすいのに対し、「音楽を創る」ではファシリテーターを含めて全員がひとつの輪を作り、その中で双方向にやりとりが行われるため、平等な関係性を保てます。
ここでもCの表現する能力を養うことにつながります。
(3)自分たちで作る

「音楽を創る」では、ピアノの技術も、五線譜を読む力も、(西洋の)音楽理論を理解しているかどうかも関係ありません(役に立ちません)。
ピアノやギターのように最初から「楽器」として作られた道具には「正しい鳴らし方」が存在します。つまりそれがあらかじめ設定されたゴールのようなものであり、そこにたどり着くのが早いこどもは「上手い」「才能がある」、遅いこどもは「下手」「才能がない」という評価につながります。
それに対して身の回りにある箱や紙切れには「正しい鳴らし方」が存在しません。どうしたら自分の好きな音・求めている音が鳴るか、何と組み合わせると鳴らしやすいか、どのように持てば疲れないか、それを踏まえてその物体をどう改良していくか…と、物理(音響)の分野まで踏み込むことでAの「音や音楽への興味関心を養い、音楽を愛好する心情を育てる」の中で特に「音」そのものへの興味関心を養うという目的を達成することができそうです。
こどもの知識や経験の差をリセットし、創造力を発揮できる環境を整えるため、「音楽を創る」ではピアノやギターといった完成された楽器や五線譜という楽譜、人の作った曲はもちろんドレミやCメジャーというような完成された音楽理論も扱いません(持ち込みを禁止しています)。
その代わりに自分に合ったオリジナルの楽器や楽譜をゼロからデザインし、それを使って音楽を創り、必要であれば音楽理論(特に音律)も自分たちでデザインします。
こうして自分たちで創造することによって、(2)の「評価しない」環境を整えやすくなります。
「音楽を創る」の流れ
まずは哲学的な問いからスタート
このプログラムは、「音楽って何?」「楽器って何?」「曲って何?」というような質問から始まります。最初にこれを考えておくと、各自がどこを目指せばよいかが明確になり、表現がスムーズになります。
ただ、それらの問いに正解はありません。そのため、こどもたちひとりひとりの中に意見が生まれ、各自がその意見を大切にしながらゴール(音楽を創る)を目指します。
プログラムの中で「音」なのか「音楽」なのか曖昧な音声を参加者に聞いてもらうと、「音だ」という意見と「音楽だ」という意見に分かれる、つまり「音」と「音楽」の境界線が人によって違うということを実際に体感することもできます。

楽器をゼロからデザインして創る
その後、自分だけのオリジナルの楽器をデザインし、実際に工作をして製作します。ここで作る楽器の材料は、身の回りに転がっている箱や紙切れで十分です。
音楽というとピアノ、ギター、ヴァイオリンといった完成された楽器が必要なように思われがちですが、必ずしもそうでないことは私の「音楽を創る」をはじめ、世界中の演奏家によって証明されています。
身の回りにあふれている物、捨ててしまうようなモノを集めて組み合わせ、生徒全員で楽器や楽譜をゼロからデザインし、それらを使って曲を作るのは資源的・経済的にも無駄がありません。
楽譜をゼロからデザインして創る
次に「楽譜」をゼロから作ります。例えば一本の線の上に好きな記号を並べ、◯が来たら箱を叩き、△が来たら指を鳴らし、✕は休む…というように、その場でしか通じないルールを作ります。

ゼロから曲を創る
最後は自分のオリジナルの楽器と楽譜を使ってオリジナルの「曲」を作ることになりますが、ここでも世の中で「正解」とされている音楽理論などは扱いません。こどもの感覚を引き出すことを最優先にしながら、ただの音をどう処理すればそのこどもにとっての「音楽」に近づくかを一緒に考え、「曲」と呼べるものを作る手助けをしていきます。
教育先進国オランダで取り入れられたプログラム
UNICEFが2013年に先進31ヶ国の物質的豊かさ、健康と安全、教育、日常生活上のリスク、住居と環境に基づいて行った調査によれば、オランダのこどもの幸福度は、あの北欧を差し置いて世界1位。日本では認可されずに「オルタナティブ教育」として特別扱いされている先進的な教育も、ごく普通に浸透しています。
実際、オランダで色々な人と話をしたりワークショップを開催していくと、自分の意見をしっかりと持ち、物事に対して受け身にならずに積極的に問題を解決していこうとする姿勢の方がとても多い印象でした。

そんな人々を育むオランダ・ユトレヒト州の4〜12歳が通う基礎学校(basisschool)の音楽教育プログラムとして2017年、「Invent Music(音楽を創る の英語版)」が取り入れられました。児童ひとりひとりがオリジナルの楽器をデザインし、グループごとにオリジナルの楽譜を話し合って作り、それらを使って曲を作るという、「音楽を創る」と同じ内容の授業です。
オランダでもここまで創造性にこだわるプログラムは珍しいようで、この話をすると現地の多くの方が興味を示してくれます。
「風景を聴く」回も
この「音楽を創る」の関連ワークとして、ワークシートを片手に耳をすませて街や自然の中を自由に歩きながら「風景を聴く」フィールドワークも用意されています。

ワークシートにはいろいろな質問が書かれていて、今聞こえている音すべてをひとつずつが大きいか小さいか、近いか遠いか、残しておきたいか消してしまいたいか、この場所にしかない音かどうか、あるいはその場所の音全体を聴いたとき、目をつぶると変化があるかどうか、その場所の音を言葉や絵で描き表すとしたらどうなるか、天気が違ったら音にどのような変化がありそうか、半年前や10年前、12時間後や50年後にはどのような音がしていそうか……といったことを考えられるようになっています。
詳しくは、単発のフィールドワークとして開催している「音さんぽ」、または音さんぽについて綴ったこちらの記事をごらんください。
音さんぽに参加された方の感想をいくつか挙げてみると───
普段はイヤホンで音楽を聞きながら歩いているので、今まで気づかなかった音・声などなどが聞けて新しい発見ができました。良い気分転換になりました。楽しかったです。
───2013/8/3 音さんぽ@大阪(天神橋筋六丁目)
自分自身を「無」にする貴重な時間でした。目を開けていると勝手に音を想像してしまうのですが、目を閉じることで、自分の体・頭をからっぽにすることができ、浄化されるような気がしました。人生の「点」を共有できたことを嬉しく思います。このワークシートおもしろいですね!聴いたこと、聞こえたことを「コトバ」にすることで、自分が居心地の良い場所がどういう所なのか分かって良いと思います。
───2013/10/20 音さんぽ@沖縄(南城、琉球ニライ大学)
こんなに時間に余裕を持って外の音を集中して聞いたことは無かったです。音楽に生かせそうです。寒い、暖かい、五感的な面で変化すると感じ方も違う。雰囲気って大事だな〜
───2013/2/17 音さんぽ@名古屋(大須)
目を閉じて聴こえてくる音に集中してみると、普段気づかなかった音が聴こえてきたり、こういう音があったらいいのにとか、耳ざわりに感じる音があったりしました。普段写真を撮る時に目に見えるものばかり意識していたので音にも意識を向けてみるとまた表現が 変わってくるのかなと思いました。
───2013/9/15 音さんぽ@鹿児島(天文館)

ふだん視覚中心の生活を送っているコトを再認識しました。自分の中での聴覚を持つ意味合いを考えてみたいと思います。
───2013/10/20 音さんぽ@沖縄(南城、琉球ニライ大学)
初めて音さんぽに参加して、音の種類や性質にすごく興味がわきました。音楽ではなく、身近にある音でこんなにも味わうことができると思ってびっくりしました。音を人に伝える際の難しさを感じ、せっかく感じたことは伝えられるようになりたいと思いました。
───2013/7/21 音さんぽ@東京(中野)
普段している音が、あらためて聞くことによりたくさん音がしている事に驚き、家に居る時TVをなるべく消そうと思った。
───2013/9/21 音さんぽ@大分(豊後高田、国東半島アートプロジェクト長崎鼻ワークショップ『音さんぽ』)
街中でも意外と多くの音が鳴っていて、ひとつずつは普通なのに集まることによって「生活」とか「人のいる場所」の音に変わっていく感じが不思議だった。自転車のチェーンや走り出す音、スタンドの音は好き(普通)だけど、ブレーキの音は好きじゃないんだなあと思った。
───2013/8/3 音さんぽ@大阪(天神橋筋六丁目)
皆さまの感想からわかることは、自分たちで新しく何かを作ったり、変化を起こしたりしなくても、すでにある空間・環境でさえ人の考え方・捉え方にこれほど多くの変化を生むことができる、ということです。

これはまさにDの「鑑賞する能力や感性を育む」だけでなく、皆さまの感想にある通り、ここでは音や音楽を飛び越えて日常生活の変化が見込めることもわかります。つまりBの「音楽によって生活を豊かにする」という目的も達成することができそうです。
このフィールドワークで分かることのひとつに「他人の音の聴き方」があります。
同じ音でも、自分と他人では違う音の聴き方をしていることもあれば、自分には聞こえていない音が他人には聞こえていることもある、というようなことを知ることで、個性や多様性を認める機会も生まれそうです。
学校の先生方へ
授業の監修や体験ワークショップ、講演などの実施も可能ですので、音楽の授業の設計にお困りでしたら「音楽を創る」概要ページのご依頼フォームからお気軽にお問い合わせください。
こちらの有料記事の内容をお読みいただき、ご自身で実施いただくことも可能です。購入をご希望の方はお問い合わせフォームからご連絡ください。
楽器メーカーの方へ
児童・生徒が考案したオリジナル楽器の製造にご協力いただける楽器メーカー様を探しています。楽器製造の技術を、新しい音楽教育の現場に活かしませんか。
お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
まとめ
私自身、幼稚園〜音楽学校まで音楽教育を受け続けたのちに音楽表現での行き詰まりを経験し、音楽教育の方向性に疑問を持ったことが「音楽を創る」を始めるきっかけとなりました。
本来、個性や創造性を守りながら伸ばし、表現を促すことは音楽や美術などの芸術系教科が最も得意とすることであったはずですが、いつの間にか他の教科と同じく画一的な基準・点数で評価されるようになり、その存在意義を問われるようになってしまいました。
そんな中、こうして新しい選択肢を提示することで、一人でも多くの方のお役に立つことができれば嬉しく思います。
参考文献・出典
筆者
世界にひとつだけのオリジナルの楽器をデザインし、五線譜ではない楽譜やドレミではない音律をグループで話し合って作り、それらを使って音楽をゼロから創作する音楽教育プログラムを中心に、音(楽)にまつわるユニークな取り組みをしています。お仕事のご依頼やコラボレーションのご提案など、お気軽に!
記事をシェアする
関連記事
テーマから探す 検索 人気の記事