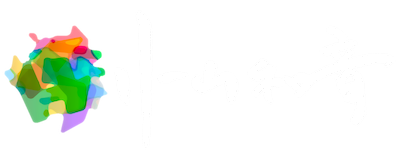音楽家が選ぶライブ用耳栓のおすすめ6選
更新 2026年1月9日

おすすめのライブ用耳栓を、音楽家の目線からご紹介します。コンサート、スタジオ、バンドなどに。
ライブ用耳栓は効果があるか、ライブ用耳栓は失礼かどうか、子供用のライブ用耳栓があるかどうかについても解説します。
もくじ
- 結論:ライブ用耳栓のおすすめ
- ライブで耳栓が必要な理由
- ライブで耳栓は失礼か?
- ライブ用耳栓の選び方
- ライブ用耳栓のおすすめ
- 長時間でも疲れないプロ向けのライブ用耳栓
- 手遅れにならないうちにどうか耳栓を
- 参考文献・出典
結論:ライブ用耳栓のおすすめ
ライブやスタジオで耳を守るには、このような「ライブ用耳栓」をおすすめします。詳しくは記事の最後で解説します。
ライブで耳栓が必要な理由
ヒトの耳に極端に大きな音が入ると、鼓膜の内側にある蝸牛(かぎゅう)というかたつむりのような形をした器官がダメージ(音響外傷)を受け、耳鳴りや聴力の低下が起こります12。

音楽関係者やライブに頻繁に通う方、あるいはイヤホン・ヘッドホンで大音量の音楽を聴く習慣がある方のように日常的に大音量にさらされている方は、特に注意が必要です。
筆者の周りで日頃大音量に晒されている方のなかにも、バンド練習やライブの後突然耳鳴りがひどくなったり、音が響いたりという症状の方がいました。もちろんその方々は耳栓をしていません。
こういった症状は音楽関係者やライブによく行く方の間で正しく知られておらず、知っていたとしても自分は大丈夫、と甘く見ている方が多い印象です。それは耳栓をしている人がいかに少ないかが物語っています。
ライブの音はどのくらい危険か
音の大きさをdB(デジベル)という単位で表します(数が大きいほど大きな音です)。
機械に聞こえる音とヒトに聞こえる音には違いがありますが、ヒトに聞こえている(ヒトの感覚に近い)数値で表したものは「A特性」と呼ばれ、dBの後ろにAや(A)が付けられています。
身の回りの音の大きさの目安は下記のとおりです。
()内は測定距離や測定条件を表しています。
値はすべて筆者が自身で測定したものです。測定対象によって異なる可能性を考えて、最も近い5dB刻みの数から±5dBの幅を持たせています(例えば92.3dBなら90dBとして、85〜95dBと表記)。
測定に使用したマイクはDayton Audio iMM-6(キャリブレーション済)、アプリはNIOSH Sound Level Meterですが、測定機材や方法によって多少変化する可能性があります。あくまでも目安としてお考えください。
| 音の大きさ (Leq) [dB(A)] | 目安 (測定距離・条件) |
|---|---|
| 30〜40 | 静かな室内 |
| 35〜45 | 図書館の館内 |
| 45〜55 | 日中の住宅街 |
| 55〜65 | コンビニの店内 |
| 60〜70 | スーパーの店内 |
| 65〜75 | 混雑した飲食店 |
| 70〜80 | 大通りの交差点 |
| 70〜80 | 混雑したショッピングモールの構内 |
| 80〜90 | 混雑した駅の改札前 |
| 80〜90 | グランドピアノ(1m/大屋根半開) |
| 85〜95 | 地下鉄の車内(急カーブ区間) |
| 85〜95 | ドライヤーの音(1m/風量最大) |
| 90〜100 | ペットボトルを潰す音(1m) |
| 90〜100 | 混雑した駅のホーム |
| 95〜105 | ドラムを叩く音(1m) |
| 110〜120 | 鉄道の高架下(列車通過時) |
一例としてWHO(世界保健機関)が作成したガイドラインでは、音を「安全に」聴くことができる上限を大人は1週間あたり80dB(A)を40時間、聴覚が敏感な人(子どもなど)は1週間あたり75dB(A)を40時間、と定めています3。
その上限値から計算すると、おおよそ次のような結果になりそうです。
| 音の大きさ [dB(A)] | 1週間あたりの限度 (大人) | 1週間あたりの限度 (子どもなど敏感な人) |
|---|---|---|
| 75 | – | 40時間 |
| 77 | – | 25時間12分 |
| 80 | 40時間 | 12時間36分 |
| 83 | 20時間 | 6時間18分 |
| 86 | 10時間 | 3時間9分 |
| 89 | 5時間 | 1時間34分30秒 |
| 92 | 2時間30分 | 47分15秒 |
| 95 | 1時間15分 | 23分37秒 |
| 98 | 37分30秒 | 11分48秒 |
| 101 | 18分45秒 | 5分54秒 |
| 104 | 9分22秒 | 2分57秒 |
| 107 | 4分41秒 | 1分28秒 |
また、アメリカのNIOSH(国立労働安全衛生研究所)では、業務において1日にさらされる騒音の「限度量」を次のように数値化しています4。
| 音の大きさ [dB(A)] | 1日あたりの限度 |
|---|---|
| 85 | 8時間 |
| 88 | 4時間 |
| 91 | 2時間 |
| 94 | 1時間 |
| 97 | 30分 |
| 100 | 15分 |
さらに、EU加盟国では8時間の平均が85dBを超える環境で働く労働者には耳栓などの防具の着用が義務付けられています5。
音楽ライブやスタジオ練習、クラブの場合、会場の特性やスピーカーの特性、イコライジング(音の成分調整)、スピーカーの音量、スピーカーからの距離や角度、楽器編成や演奏内容などによって様々ですが、少なくとも90dB以上の音量に数時間晒され続けるケースが多いのではないかと思います。
ノルウェー科学技術大学のMorten Andreas Edvardsen氏がノルウェー国内50ヶ所の会場で行われた621回のコンサートを調査したところ、大部分のコンサートが15分平均で90dB(A)を超え、14%のコンサートは15分平均で102dB(A)を超えていた6とのことです。
ライブによく行かれる方で、実際ご自分がどのくらいの音量にさらされているのかを知りたい方は、例えば下記のような、スマートフォンに直接挿して使える小さな測定用マイクと測定アプリでチェックすることもできます(スマートフォンの内蔵マイクでは正確性に欠けるため、測定用マイクの使用をおすすめします)。
- 測定マイク
- ヘッドセット(マイク付きイヤホン)端子のあるスマートフォンの方:Dayton Audio iMM-6
- USB-C端子のスマートフォンの方:Dayton Audio iMM-6C
- Lightning端子のiPhoneの方:Apple Lightning-3.5mm ヘッドフォンジャックアダプタ MMX62J/A (A1749) + Dayton Audio iMM-6
- 測定アプリ
- NIOSH Sound Level Meter(無料/iPhoneのみ)
- Studio Six Digital SPL Pro(無料/iPhoneのみ):録音・録画機能は誤解を避けるため使用しないことをおすすめします

これらの数値を基準に考えると、ライブやスタジオ練習、クラブなどは耳にとってかなり危険な環境であると言えるでしょう。
こうなってしまった原因は、ライブそのものの音量設定の感覚や基準が狂っている(音楽を純粋に楽しむために必要な音量をはるかに超えている)ことだと私は考えています。
耳栓なしで耳を酷使していた筆者の場合
筆者も高校時代、狭い部屋に置いたドラムを耳栓なしで長時間叩いたり、大きな音量でモニター(確認)しながら音楽制作をしたり、大音量の音楽をイヤホン・ヘッドホンで聴いたりということを日常的に行っていました。
するとある日突然耳の異常な不快感に襲われ、苦痛のあまり一切音楽活動ができなくなり、数ヶ月に渡って入っていたすべてのライブをキャンセルしなければいけませんでした。
ひどい時には人の笑い声でもこの反応が出たことがあり、もちろん楽器は何ヶ月も弾けないし、音楽を聴くことすらできず、このまま耳が聞こえなくなるのだろうか?という恐怖と闘う日々を過ごしました。
筆者はここで耳の使い方を反省してEtymotic Researchの耳栓「ER20」を買い、なるべく大きい音を聞かないように注意しながら徐々に音楽活動を再開しました。
幸いこれは数年をかけてゆっくりと回復しましたが、こうならないための唯一の方法は、「大きな音を聴かない」(鼓膜に大きな音を届けない)こと、つまり耳栓をすることです。
イヤホンやヘッドホンで音楽を聴く場合は音量を下げればよいのですが、ライブやスタジオなど自分のコントロールがきかない状況では耳栓をするしかありません。
目は閉じることができても耳は閉じられないので、これ以外に方法がありません。
ライブで耳栓は失礼か?
ライブで耳栓をするのは失礼な行為なのでしょうか?
筆者は職業柄、音楽関係の友人が多いですが、耳栓が失礼だと言っている音楽関係者は見たことがありません。ステージに立つ側であった私ももちろん、そんな発想には至りませんでした。
個人的には、これは過剰なマナー意識が一人歩きをしてしまい、ステージに立つ人間は何とも思っていないのに、観客側が「失礼だからやめておこう」と一方的に遠慮してしまっている状態なのではないかと想像します。
誰かが本当に「失礼だ」と言っていたとしたら、きっとその方は音響外傷を負ったこともなければ、ステージに立てない悔しさや、仕事がなくなる不安、そして耳が聞こえなくなるかもしれないという恐怖を味わったこともないのでしょう。このような経験をして、そうならないための唯一のツールが耳栓だということを学んでいれば、こんな発言はできないはずです。
それに、「失礼」という感覚は主観的なもので、人それぞれ感じ方が違うものです。
たまたま「失礼」と感じる珍しい人に耳栓をしているところを見られたところで、私たちの人生には何の影響もありません。自分の耳の生死と比べたときにどちらか大切かで決めるとよいでしょう。
そもそも、
- ライブ用耳栓は正面からほとんど見えないデザインのものが多いです。横から見ても目立たないものも珍しくありません。
- 屋内のライブは特に客席側が暗いので、ステージから観客の方々はあまりよく見えません。顔がやっと見えるくらいです。
一例として、これはLoopの耳栓「Quiet 2」「Switch 2」「Dream」それぞれの正面からの見え方です。

ということで、出演者から観客の方を見たときに、耳栓をしているかどうかはまずわかりません。安心して耳栓をしてください。
最近は公式グッズとしてライブ用耳栓の販売を始めた有名バンドもあるくらいなので、音楽関係者がようやく大音量の危険性に気づき始めたとも言えます。
耳栓を「マナー違反」としたり不快に思う音楽関係者は、認識が遅れていると言わざるをえません。そのような方は、自分の耳が壊れてからようやく過ちを認めることになります。
ライブ用耳栓の選び方

音の聞こえ方は人によって違いますし、耳の形や大きさ、遮りたい音の成分や大きさ、耳栓を使うシチュエーションや脱着の頻度によって最適な耳栓は変わってきます。
一般的に耳栓は、例えば低い音はたくさん聞こえるが高い音はあまり聞こえないなど、音の高さによって聞こえ方が違います。
そのため、耳栓を選ぶ上では「どの高さの音をどのくらい遮れるか」が重要なのですが、これを測定・算出するときにメーカーによってばらつきが出ないように統一された規格が存在します。
- アメリカではEPA(米国環境保護庁)が定めたNRR(ノイズ・リダクション・レイティング)という規格
- ヨーロッパでは主にISO 4869-2で規定されたSNR(シングル・ナンバー・レイティング)という規格に則って「どの高さの音をどのくらい遮れるか」という数値
を公表しています。
しっかりとしたメーカーならば測定結果をすべて表にまとめ、NRRかSNRのどちら(あるいは両方)の値であるか、どの規格に準拠しているかが明記されていますが、そのようなメーカーはあまり多くありません。
まとめると、ライブ用耳栓を選ぶ場合、筆者としては
- SNR値やNRR値が明記されている
- 準拠する規格(「EN 352-2:2020」や「ANSI S3.19-1974」)が明記されている
- 各周波数ごとの遮音性能が表にまとめられている
これらの条件を満たしている耳栓をおすすめします。
NRRとSNRは算出方法が違うため、NRRの数値とSNRの数値を比べても意味がありません。比べる場合はNRR同士、SNR同士でなければいけません。
今回ご紹介する耳栓はすべてEN 352-2:2020に準拠したSNR値であると明記されているので、信頼できる数値とみてよいでしょう。
耳栓本来の遮音性能を発揮するには、耳栓を正しく装着する必要があります。装着方法はそれぞれの耳栓の取扱説明書をご確認ください。
ライブ用耳栓は効果があるか
SNR値や準拠する規格を明記している耳栓であれば効果があるといえますが、明記していない耳栓については効果が疑わしいと判断してよいでしょう。
効果のある耳栓は、遮音性能の分だけ音をカットしてくれます。
例えば90dBの音が聞こえているとき、遮音性能が20dBの耳栓を正しく付けることで、理論上耳に届く音は90 – 20 = 70dBになります。
これは理論上の数値ですので、実際に耳に届く音にはある程度の個人差が見込まれます。
子供向けのライブ用耳栓
遮音性能の数値が信頼できるメーカーから子供向けとして発売されている耳栓は、2025年10月現在LoopのEngage Kids 2のみです。
このEngage Kids 2は特にライブ用という位置付けではありませんが、ライブに使えないということはありません。
遮音レベルが平均16dBと低めに設定されているため、あまり大音量のライブではおすすめできませんが、学校や教室の発表会程度の音量であれば許容範囲内かと思います。
Engage Kids 2の遮音バランスやLoopの他の耳栓との違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
耳栓とイヤープラグの違い
耳栓を英語で言うとイヤープラグ(earplug)なので、耳栓=イヤープラグです。
ライブ用耳栓は国外メーカーのものが多いので「耳栓」ではなく「イヤープラグ」とも表記されていることが多い印象ですが、どちらも機能に違いはありません(この記事では「耳栓」に統一しています)。
個人的には、
- 「耳栓」:音のバランスよりも遮音を重視した使い捨ての聴覚保護具
- 「イヤープラグ」:生活やファッション、文化の一部として繰り返し長く使えるツール
という印象を受けます。
ライブ用耳栓のおすすめ
ライブ用耳栓は音楽ライブやスタジオでの演奏を前提に設計されていますが、耳栓によって遮音バランス(どの高さの音をどのくらい減らすか)が違うため、ご自身の好みや方向性に合わせて耳栓を探してみてください。
使い捨ての耳栓と比べると高く感じるかもしれませんが、一度買えばずっと耳を守り続けてくれるものです。音楽関係者や音楽好きの方へのプレゼントとしても良いかもしれません。
おすすめライブ用耳栓1:Crescendo Music 20(最も安い)

オランダの音響フィルターメーカーDynamic Ear Company B.V.が手がける耳栓ブランドCrescendo(クレッシェンド)のMusic 20。
今回ご紹介する耳栓の中では最も安いですが、遮音レベルはやや低めです。
予算が限られている方や、そこまで大音量のライブに行かない方には向いています。
ストラップが付属しないため、頻繁に耳栓の付け外しをする場合には煩わしく感じるかもしれません。
| メーカー | |
| イヤーピース | S、M、L |
| フィルター | 1種類 |
| ストラップ (首にかけられるヒモ) | なし |
| 専用ケース | 付属 |
| カラー | トランスパレント (透明) |
| 遮音性能の測定・算出規格 | EN 352:2-2020 |
音の高さごとの遮音性能はこのとおりです。
グラフの左に行くほど低い音、右に行くほど高い音で、線が下にあるほど遮音性能が低く(あまり音を遮れず)、上にあるほど高い(音をよく遮れる)といえます。
| 周波数 [Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遮音性能 [dB] | 14.4 | 15.1 | 15.4 | 17.1 | 19.9 | 26.9 | 17.7 | 29.9 | 19.6 |
おすすめライブ用耳栓2:Loop Quiet 2 (Plus)

ベルギーの耳栓メーカーLoop(ループ)のQuiet 2 (Plus)。
特にQuiet 2は今回ご紹介する耳栓の中ではCrescendo Music 20の次に手頃な価格でありながら、他社の耳栓と比べても高い遮音性能を誇ります。
よい意味で「耳栓っぽさ」がなく、アクセサリーのように見えるデザインもLoopの耳栓の特徴です。
予算に限りがある・コストパフォーマンス重視の方にはQuiet 2 (Plus)をおすすめします。
Quiet 2 PlusについてとQuiet 2とQuiet 2 Plusの違いについては、こちらの記事で詳しくレビューしています。
音の高さごとの遮音性能はこのとおりです。
グラフの左に行くほど低い音、右に行くほど高い音で、線が下にあるほど遮音性能が低く(あまり音を遮れず)、上にあるほど高い(音をよく遮れる)といえます。
| 周波数 [Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ear Tipsの 遮音性能 [dB] | 23.3 | 24.1 | 20.9 | 21.3 | 25.9 | 31.0 | 33.0 | 24.4 | 26.0 |
| Double Tipsの 遮音性能 [dB] | 26.0 | 26.0 | 25.6 | 24.5 | 24.6 | 33.3 | 31.6 | 36.3 | 27.0 |
おすすめライブ用耳栓3:Etymotic Research ER20 / ER20XS

アメリカ・イリノイ州の、イヤホンや耳栓を専門とするメーカーEtymotic Research(エティモティック・リサーチ)のER20とER20XS。
ER20とER20XSの遮音性能はほとんど同じですが、ER20は本体のステム部分が長くER20XSは短いという違いがあり、ER20はステム(耳栓から飛び出た棒状の部分)が長いぶんER20XSに比べると少し目立ちやすい一方、脱着はしやすいです。
筆者はER20を長年使ってきましたが、演奏のニュアンスや迫力は問題なく感じ取ることができ、耳栓をつけた状態でつけていない状態の音(実際に観客に届いている音)をイメージしながら音を出すこともできるようになりました。
音響外傷で苦しんでいた時期に使い始めましたが、耳は時間をかけて完全に回復したことから、ライブ用耳栓としての効果・意味があったと言えます。
イヤーピースの大きさやフランジ(ヒダの数)によって製品が細かく分かれていてわかりにくいため、表にまとめました。
イヤーピースは直接耳にフィットする部分なので、耳が大きめの方はイヤーピースが「L」のものを選んでもよさそうですが、北米/ヨーロッパの人の基準で「L」となると、日本の人の耳には大きすぎる可能性もあります。
「UF」が付くものはイヤーピースのSとLがどちらも付属しますので、そちらが無難かもしれません。ただしUFがあるのはER20XSだけで、ER20には見当たりませんでした。
画像をタップ/クリックすると商品ページにジャンプします。
ER20XSのバリエーションを見る
| メーカー | |
| イヤーピース | 上の表を参照 |
| フィルター | なし (イヤーピース自体がフィルター) |
| ストラップ (首にかけられるヒモ) | 付属 |
| 専用ケース | 付属 |
| カラー | クリア(透明) |
| 遮音性能の測定・算出規格 | EN 352-2:2020 |
音の高さごとの遮音性能はこのとおりです。
グラフの左に行くほど低い音、右に行くほど高い音で、線が下にあるほど遮音性能が低く(あまり音を遮れず)、上にあるほど高い(音をよく遮れる)といえます。
| 周波数 [Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER20の 遮音性能 [dB] | 15.2 | 11.4 | 14.5 | 17.3 | 20.5 | 22.6 | 21.3 | 26.1 | 18.6 |
| ER20XSの 遮音性能 [dB] | 14.8 | 10.4 | 14.2 | 17.7 | 18.9 | 21.0 | 20.9 | 30.3 | 18.5 |
おすすめライブ用耳栓4:Sennheiser SoundProtex
プロフェッショナルの現場で数多く採用される業務用のイヤホン、ヘッドホン、マイクなどを手がけるドイツの音響機器メーカーSennheiser(ゼンハイザー)のSoundProtex。
低音〜中音くらいまではバランスよく高い遮音性ですが、それより高い音はあまり遮らなくなるという珍しい特性を持ちます。
3種類のイヤーピース(S、M、L)と2種類のフィルター(ミッドフィルター、フルブロックフィルター)が付属します。
| メーカー | |
| イヤーピース | S x 1ペア、 M x 1ペア、 L x 1ペア |
| フィルター | ミッドフィルター、 フルブロックフィルター |
| ストラップ (首にかけられるヒモ) | なし |
| 専用ケース | 付属 |
| カラー | ブラック |
| 遮音性能の測定・算出規格 | EN 352-2:2020 |
音の高さごとの遮音性能はこのとおりです。
グラフの左に行くほど低い音、右に行くほど高い音で、線が下にあるほど遮音性能が低く(あまり音を遮れず)、上にあるほど高い(音をよく遮れる)といえます。
フルブロックフィルターの値は見当たらず、フェスやコンサートに適しているというミッドフィルターの数値で比較しています。
| 周波数 [Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遮音性能 [dB] | 21.4 | 23.6 | 22.8 | 22.7 | 25.8 | 22.8 | 15.8 | 17.4 | 21.1 |
おすすめライブ用耳栓5:Alpine MusicSafe Pro
TPR(ホワイト)
BLK(ブラック)
オランダの耳栓専門メーカーAlpine(アルパイン)のMusicSafe Pro。
低い音はそれほど遮らず、高い音になるほどよく遮るようになります。
- Gold(強力な遮音)
- Silver(中程度の遮音)
- White(簡単な遮音)
という3種類のフィルターが付属するため、例えば演奏のニュアンスよりも耳の保護を優先したい時はGoldを、ニュアンスを正確に感じ取りたいときはSilverを、というように状況に応じて柔軟に対応できます。
| メーカー | |
| イヤーピース | 内蔵(交換不可) |
| フィルター | Gold x 1ペア、 Silver x 1ペア、 White x 1ペア |
| ストラップ (首にかけられるヒモ) | 付属 |
| 専用ケース | 付属 |
| カラー | TPR(ホワイト)、 BLK(ブラック) |
| 遮音性能の測定・算出規格 | EN 352-2:2020 |
それぞれのフィルターの、音の高さごとの遮音性能はこのとおりです。
グラフの左に行くほど低い音、右に行くほど高い音で、線が下にあるほど遮音性能が低く(あまり音を遮れず)、上にあるほど高い(音をよく遮れる)といえます。
| 周波数 [Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldフィルターの 遮音性能 [dB] | 15.7 | 17.8 | 19.2 | 21.4 | 22.9 | 27.3 | 27.4 | 29.4 | 22.6 |
| Silverフィルターの 遮音性能 [dB] | 11.6 | 13.5 | 15.4 | 17.4 | 18.7 | 24.6 | 25.1 | 31.4 | 19.7 |
| Whiteフィルターの 遮音性能 [dB] | 6.2 | 5.6 | 8.7 | 10.7 | 15.9 | 23.6 | 24.2 | 29.5 | 15.6 |
おすすめライブ用耳栓6:EarLabs(D’Addario)dBud
スウェーデンの耳栓メーカーEarLabs(イアラブズ)のdBud。
EarLabsブランドのものはAmazonや楽天では販売されていませんが、ギターの弦で有名なメーカーD’Addario(ダダリオ)ブランドのものはAmazonや楽天でも販売されています(どちらも遮音性能は同じです)。
装着したまま開閉(遮音する量を調整)できる珍しい耳栓であり、今回ご紹介する耳栓の中では全体的に最も遮音性能が高いです(閉じた状態で比較しています)。
- 本体のボタンをスライドするだけで遮音量を変えられるため、ライブ中は閉じておき、話しかけられたら開くといった使い方もできます。
- 上3つの耳栓と比べると高価です。
- 耳栓本体にマグネットが内蔵されており、装着していない時(ストラップを首にかけた状態)はネックレスのような状態になります。
| メーカー | |
| イヤーピース | シリコン5種類(XS、S、M、L、XL) * EarLabs版には追加でメモリーフォーム3種類(S、M、L)が付属するようです |
| フィルター | なし (イヤーピース自体がフィルター) |
| ストラップ (首にかけられるヒモ) | 付属 |
| 専用ケース | 付属 |
| カラー | チャコールブラック * EarLabs版にはダスティピンクもあるようです |
| 遮音性能の測定・算出規格 | EN 352-2:2020 |
開閉部を閉じた状態での、音の高さごとの遮音性能はこのとおりです。
グラフの左に行くほど低い音、右に行くほど高い音で、線が下にあるほど遮音性能が低く(あまり音を遮れず)、上にあるほど高い(音をよく遮れる)といえます。
| 周波数 [Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閉めた状態の 遮音性能 [dB] | 23.8 | 21.4 | 21.6 | 21.0 | 24.4 | 30.7 | 28.0 | 27.5 | 24.8 |
| 開いた状態の 遮音性能 [dB] | 8.4 | 5.7 | 6.9 | 7.6 | 10.5 | 18.3 | 21.8 | 21.2 | 13.1 |
ライブ用耳栓の性能・効果を比較
上でご紹介したグラフを重ねてみました。
1つの耳栓に複数のフィルターや開閉機構がある場合は最も遮音値が大きい状態のグラフのみを載せています。
グラフの左に行くほど低い音、右に行くほど高い音で、線が下にあるほど遮音性能が低く(あまり音を遮れず)、上にあるほど高い(音をよく遮れる)といえます。
つまりこの線が平らなほど、どの高さの音もバランスよくカットするということになります。
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 | 15.1 | 15.4 | 17.1 | 19.9 | 26.9 | 17.7 | 29.9 | 19.6 | |
(Double Tips) | 26.0 | 26.0 | 25.6 | 24.5 | 24.6 | 33.3 | 31.6 | 36.3 | 27.0 |
| 14.8 | 10.4 | 14.2 | 17.7 | 18.9 | 21.0 | 20.9 | 30.3 | 18.5 | |
| 21.4 | 23.6 | 22.8 | 22.7 | 25.8 | 22.8 | 15.8 | 13.5 | 21.1 | |
(Gold) | 15.7 | 17.8 | 19.2 | 21.4 | 22.9 | 27.3 | 27.4 | 29.4 | 22.6 |
(閉めた状態) | 23.8 | 21.4 | 21.6 | 21.0 | 24.4 | 30.7 | 28.0 | 27.5 | 24.8 |
まとめると、次のような選び方になりそうです。
確かに遮音性能が高ければ高いほど耳にとっては優しいですが、音楽関係者や音楽好きの方にとっては細かい音のニュアンスや迫力を犠牲にする可能性があるため、一概に遮音性能が高いものだけがおすすめとは言えず、どの程度の遮音性を求めるかで選ぶ耳栓が変わってきます。
また、装着感も耳栓によって・それぞれの耳の形によって変わってくるため、こればかりは使ってみないと何とも言えません。
長時間でも疲れないプロ向けのライブ用耳栓
筆者は上でご紹介したER20を買ってしばらくしてから、アメリカ・イリノイ州にあるイヤーモニターメーカーSensaphonics(センサフォニクス)のMusician’s Ear Plugsを使うようになりました。

このMusician’s Ear Plugsは補聴器店などで耳型を採って作るオーダーメイドのライブ用耳栓(日本でも耳型を採って注文できます)で、音のバランスはほとんど変えずに音量だけ下げてくれるだけでなく、自分の耳専用に作られているため長時間つけていても耳が痛くなりにくく重宝しています。
9dB・15dB・25dBカットのフィルターをそれぞれ左右別に選べるので、例えばヴァイオリニストは左耳用を15dBカット、右耳用を9dBカットというようにアレンジできます。
少し値段は張りますが、一生耳を守れると思えば安いものです。
また、この耳栓は肌色に近い色をしていて耳にすっぽり埋まるため、口を大きく動かしてもずれることがなく、装着していても外からはほとんど分かりません。写真映りを気にしなくても大丈夫です。
ただし上でご紹介した耳栓のように首からかけられるヒモは付けられないため、着脱の多い現場やさほど遮音の必要ない場面ではER20を使うようにしていました。
手遅れにならないうちにどうか耳栓を
目は閉じられても、耳は閉じられません。
目をそむければ見えなくなりますが、耳をそむけても音は耳に入ってきます。
となれば、耳は自分で守るしかありません。手遅れにならないうちに。
音楽に関わり、音楽を愛するすべての方へ。
耳栓を強くおすすめします。
参考文献・出典
- 和田哲郎、騒音性難聴の最近の知見 (疫学, 基礎など) 日本耳鼻咽喉科学会会報 2017年 120巻 3号 p.252-253, doi:10.3950/jibiinkoka.120.252 ↩︎
- 和田哲郎、原晃:職域に生かす耳鼻咽喉科の最新知識 騒音性難聴① 歴史と医学的・社会的背景 産業医学ジャーナル Vol.38 No.6 2015 ↩︎
- WHO Environmental noise guidelines for the European Region,
section 3.5, Recommendation for leisure noise exposure. Copenhagen:
World Health Organization; 2018 ↩︎ - NIOSH [1998]. Criteria for a recommended standard: occupational noise exposure. DHHS (NIOSH) Publication Number 98-126. ↩︎
- Directive 2003/10/EC of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) ↩︎
- Analysis of measurements from Norwegian venues for amplified music, section 5.2. Morten Andreas Edvardsen, Norwegian University of Science and Technology ↩︎
筆者
世界にひとつだけのオリジナルの楽器をデザインし、五線譜ではない楽譜やドレミではない音律をグループで話し合って作り、それらを使って音楽をゼロから創作する音楽教育プログラムを中心に、音(楽)にまつわるユニークな取り組みをしています。お仕事のご依頼やコラボレーションのご提案など、お気軽に!
記事をシェアする
関連記事
テーマから探す 検索 人気の記事