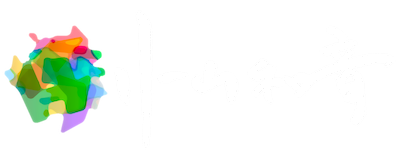DTM・配信・YouTube収録におすすめのモニターヘッドホン3選
更新 2025年10月6日

レコーディング(DTM)・配信・YouTube収録などに必要なモニターヘッドホンのおすすめをまとめました。
モニターヘッドホンとは
DTMや配信、収録や放送などにおいて「今、どのような音なのか」をチェックするためのヘッドホンを特に「(スタジオ)モニターヘッドホン」と呼びます。
モニターヘッドホンはリスニング用のヘッドホンのように「快適に音を楽しむ」といったコンセプトではなく「業務用のチェックツール」のような位置付けのため、一般的にリスニング用のヘッドホンと比べて
- 音の成分のバランスがよい(聞き手が再生するときの音をイメージしやすい)
- より多くの音が聞こえる(ノイズが乗っていればよりはっきりと聞こえる)
- より音の位置が見えやすい
という傾向があります(あくまでも傾向のため、すべてのヘッドホンが当てはまるわけではありません)。
基本的にいわゆる「いい音」を目指して作られたものではないため、それを求めて買うものではありませんし、音が見えすぎることで長時間の作業では疲れてしまうこともあります。
時には「音質が悪い」と感じることがあるかもしれませんが、それは再生している音源や録音している音の方にある問題をしっかり伝えてくれている可能性もあります。
このように、普通のヘッドホンとは少し役割が違うのだということを理解したうえで、モニターヘッドホンを選んでみてください。
どのようなモニターヘッドホンがよいか
まずは音のバランスのよさを追求
世の中にはいろいろな方向性のモニターヘッドホンがありますが、最初の1台としてはなるべく成分のバランスのよい(クセの少ない)音を目指して作られたヘッドホンをおすすめします。
最初から「クセ(色付け)」が強いヘッドホンを使ってコンテンツを作ってしまうと、他のスピーカーやヘッドホンで聴いたときに、まったく想定していなかった味(音)になってしまう可能性があるためです。
最初の1台ということは他に比較対象となるヘッドホンがなく、自分の中の唯一の「音の基準」がそのヘッドホンになるということでもあるのですが、音のバランスのクセの強いヘッドホンが基準になった状態では「その音がどういう音なのか(他の機器ではどのように聞こえるのか)」を想像しにくくなります。
そのヘッドホンの音が他のヘッドホンと比べてどのように違うかを理解していて、あえてその音を求めてそのヘッドホンを買うのであればよいのですが、最初の1台となるとまずは他のヘッドホンとどのように違うのかを判断しやすい(なるべく中立的な)音の基準を自分の中に確立した方が将来的な後悔が少なくなるのでは、と筆者は考えています。
長時間使う場合は音のバランスよりも聴き疲れのしにくさを優先
ただし、音の成分のバランスのよいヘッドホンは聴いていて気持ちのよい音とはまた違うため、聴き疲れをしやすい可能性があります。
壁が薄い、夜間に使うなどのやむを得ない理由でモニタースピーカーの代わりとしてヘッドホンを使う場合は、音のバランスよりも聴き疲れのしにくさを優先してもよいと思います。
ただ、耳への負担を考えて、可能な限り小さい音量でモニタリングすることをおすすめします。
おすすめのモニターヘッドホン
ヘッドホンのメーカーは通常、そのヘッドホンの仕様や音の特性の測定結果を公表しているのですが、「どのような音のバランスか」については基本的に掲載されていないか、されていてもメーカーごとに測定方法が違うため、販売店やレビュアーなどの第三者や研究機関などの測定結果を探すしかなさそうです。
今回はカナダの第三者測定機関RTINGS.comがテストしたヘッドホン840機種の測定結果などを参考に、なるべく音のバランスがよいと感じる人が多そうなヘッドホンをピックアップしました。
ヒトは音の高さ、年齢、個人差、耳や頭の形などによって音の聞こえ方が違うため、すべての人が「バランスがよい」と感じるヘッドホンは存在しませんが、そう感じる人が多そうなヘッドホンはいくつか挙げられます。
ただ、確率が高そうと判断する基準の選び方も難しく、正解が存在しないため、今回はさしあたり下記の基準から価格が比較的手頃なヘッドホン(有線式・オーバーイヤー型)をピックアップすることにします。
- 音のバランスを重視
- 拡散音場(Diffuse Field 5128)カーブに近いヘッドホン
- フラット(出る音がどの高さにおいても均一)なスピーカーから出る音を反響のある部屋で聴いたときの結果を表した指標です。完璧ではないが理論上は(聴覚上)原音に概ね忠実な音として聞こえる、と筆者は理解しています。
- 拡散音場(Diffuse Field 5128)カーブに近いヘッドホン
- 音の快適性を重視
- ハーマンカーブ(Over-ear 2018)に近いヘッドホン
- アメリカの音響機器メーカーHarman International Industries(ハーマン・インターナショナル)がアジア、ヨーロッパ、北米各国の幅広い年齢層・様々なリスニング経験をもつ数百人の男女を対象にブラインドテストを行い、このうち64%の被験者が好むと回答した指標です(次の21%は低音をやや削ったハーマンカーブを好むと回答)。
- ハーマンカーブ(Over-ear 2018)に近いヘッドホン
実際どのような音に聞こえるかはテストの結果からは見えづらく、再生する音源、組み合わせるオーディオインターフェース、電源、聴く人の年齢や耳の形など様々な要素が影響するため、あくまでも参考程度にお考えください。
モニターヘッドホンのおすすめ(1)audio-technica ATH-M50x
日本の音響機器メーカーaudio-technica(オーディオテクニカ)のATH-M50x。
RTINGS.comの測定結果、およびoratory1990氏がGRAS 45BC-10(人間の頭の形をした測定器具)を使って行った測定結果では70〜240Hzあたりに盛り上がりと300Hz付近に谷がみられますが、それ以外は概ねハーマンカーブ(Over-ear 2018)に沿っています。
ハーマンカーブは音のバランスの良さよりも「好きかどうか」という主観の平均値(多くの人が好む音)であるという性質から、聴き疲れにつながりにくいと仮定してピックアップしました(あくまでも可能性や傾向ですので、すべての方に当てはまるわけではありません)。
| メーカー | |
| 製品名 | ATH-M50x |
| 構造 | 密閉型 |
| 駆動方式 | ダイナミック |
| ドライバーの直径 [mm] | 45 |
| 周波数特性 [Hz – kHz] | 15 – 28 |
| ケーブルの形状 | ストレート / カール |
| ケーブルの着脱 | 可 |
| プラグ | ミニ (標準アダプタ付属) |
| 折りたたみ | 可 |
| 重さ [g] | 285 |
モニターヘッドホンのおすすめ(2)AKG K361 / K371
オーストリア発、現在はアメリカに本拠をおく音響機器メーカーAKG(エーケージー)のK361とK371。
このヘッドホンのメーカーAKGは1994年にハーマン・インターナショナルの傘下に入り、冒頭でご説明したハーマンカーブを忠実再現するように設計・チューニングが行われたK361と、その上位機種であるK371が登場しました。
oratory1990氏がGRAS 45BC(人間の頭の形をした測定器具)を使って行った測定結果でも、K361・K371どちらもきれいにハーマンカーブに沿った特性であることがわかります(K371の方がよりハーマンカーブに近いように読み取れます)。
現在はK361とK371それぞれ有線接続と無線接続の両方に対応したモデル(-BTが付く)が販売されています。型番最後尾の「-Y3」は3年保証を意味します。
スピーカーの代わりとしてやむを得ずヘッドホンを長時間使わなければいけない方には、よい選択肢となるかもしれません。
| メーカー | ||
| 製品名 | K361-BT | K371-BT |
| 構造 | 密閉型 | 密閉型 |
| 駆動方式 | ダイナミック | ダイナミック |
| ドライバーの直径 [mm] | 50 | 50 |
| 周波数特性 [Hz – kHz] | 15 – 28 | 5 – 40 |
| ケーブルの形状 | ストレート(1.2m) ストレート(3m) | ストレート(1.2m) ストレート(3m) カール(3m) |
| ケーブルの着脱 | 可 | 可 |
| プラグ | ミニ (標準アダプタ付属) | ミニ (標準アダプタ付属) |
| 折りたたみ | 可 | 可 |
| 重さ [g] | 215 | 255 |
モニターヘッドホンのおすすめ(3)Sennheiser HD600
ドイツの音響機器メーカーSennheiser(ゼンハイザー)のHD600。
crinacle氏がGRAS 43AG-7を使ったテストによれば、50Hz周辺から上は概ね拡散音場(Diffuse Field 5128)に沿っていることがわかり、100Hz周辺から上の特性はハーマンカーブ(Over-ear 2018)にもかなり近いことがわかります。
こちらは上のヘッドホンと違い、ヘッドホンの背面から振動(音)を逃がす「開放型」と呼ばれるタイプです。
そのため、ヘッドホンとマイクを同時に使う場合、ヘッドホンから漏れた音がマイクに拾われてしまう可能性がありますので、リアルタイムの配信やマイクを使ったレコーディング時のモニタリングには向きません。
| メーカー | |
| 製品名 | HD600 |
| 構造 | 開放型 |
| 駆動方式 | ダイナミック |
| ドライバーの直径 [mm] | 42 |
| 周波数特性 [Hz – kHz] | 12 – 40.5 |
| ケーブルの形状 | ストレート |
| ケーブルの着脱 | 可 |
| プラグ | ミニ (標準アダプタ付属) |
| 折りたたみ | 不可 |
| 重さ [g] | 260 |
モニターヘッドホンの選び方
駆動方式で選ぶ
ダイナミック方式
磁石と並んだボイスコイルに電流を流すとボイスコイルが前後に動き、そこに繋がれた振動板が空気を振動させます。
ダイナミックマイクと構造は同じで、電流の向きが逆になっただけです。
マグネティック(バランスド・アーマチュア)方式
ボイスコイルの片方が固定されていて、もう片方が固定されておらずその周囲に磁石が設置されており、この固定されていない部分に繋がれた振動板が空気を振動させます。
ダイナミック方式に比べて小型化できるため、イヤホンで採用されています。
静電方式
日本のSTAX(スタックス)社が世界で初めて実用化した方式で、ダイアフラム(振動膜)の両側にある電極に電圧をかけることでダイアフラムが前後に動いて空気を振動させるしくみです。
構造で選ぶ
密閉型

密閉型は、スピーカーユニットの裏側が密閉されているタイプです。よほどの大音量でない限り、装着している本人にしか音は聞こえません。
ヘッドホンによるため一概には言えませんが、下の「開放型」に比べると低い音の再現に強みを持ったヘッドホンが多い印象です。
この記事でご紹介しているヘッドホンはすべてこちらの密閉型ですので、ヘッドホンから漏れた音がマイクに入り、録音や配信に意図しない音が入り込んでしまうこともありません。
開放型

開放型は、スピーカーユニットの裏側が密閉されていないタイプです。ヘッドホンの外側にも音が聞こえ、逆にヘッドホンの外からの音も聞こえてきます。
こちらもヘッドホンによりますが、上の密閉型に比べると、高い音の伸びや自然な再現に強いヘッドホンが多い印象です。
ただしこちらはヘッドホンから音を「漏らす」構造のため、ヘッドホンを使いながらマイクで録音や配信を行う場合は、意図しない音が入り込んでしまいますのでおすすめできません。
ケーブルの脱着(リケーブル)可否で選ぶ

ケーブルの着脱(本体からケーブルを切り離す、リケーブル)に対応しているヘッドホンであれば、万が一ケーブルやプラグが破損した場合でも、本体を買い替えることなく使い続けることができます。
また、社外品のケーブルが販売されている場合はケーブルを交換することで好みの音色に近づけられるかもしれません。
モニターヘッドホンを安く買うには
モニターヘッドホンはAmazonや楽天でも買うことができますが、あわせて価格をチェックしておきたいのが日本の楽器・音響機器の総合販売店であるサウンドハウスです。
オンラインで楽器や音響機器を買おうと思ったらサウンドハウスなしでは考えられないほど、関係者の間では定番の販売店です。
商品購入後14日以内に、他店でその商品がサウンドハウスより安く販売されている場合、差額を返金、もしくは次回利用時に割引する「最低価格保証」があります。
モニターヘッドホンがあればモニタースピーカーはいらない?
特にDTMではモニターヘッドホンがあればモニタースピーカーは不要なのでは、という意見もあります。
ヘッドホンとスピーカーのどちらを選ぶべきかは、目的と状況によります。
スピーカーを鳴らしても周りに迷惑がかからない環境であれば問題ありませんが、その点で安心できない場合はヘッドホンを優先して探してみましょう。
YouTube動画の収録や楽器演奏のレコーディングなどでマイクの音声をモニタリングする時や、ライブ配信やゲーム実況など音を聴きながらマイクを使いたい時にスピーカーを使っていると、スピーカーから出た音がマイクに拾われてしまいます。
そうすると収録やレコーディングでは録れた音が二重に聞こえてしまったり、配信や実況では不要な音まで配信されてしまい、どちらもクオリティが低いような印象を与えてしまうことがありますので、そのような場合は(密閉型の)ヘッドホンをおすすめします。
一方で、ヘッドホンは長時間の作業では疲れやすかったり、耳への負担が大きいという問題点もあります。基本的にマイクを使っていない時のモニタリングはスピーカーを使って問題ありません。
おすすめのスピーカーはこちら。
関連機材のおすすめ
オーディオインターフェース

モニターヘッドホンをパソコンやスマホに接続するには、オーディオインターフェースと呼ばれる機器を使います。
オーディオインターフェースは、USBやThunderboltでパソコンやスマホと繋ぐ「音の出入り口」のようなものです。オーディオインターフェースのおすすめはこちら。
ヘッドホンハンガー

ヘッドホンはデスクに置いておけますが、なにかとスペースをとるので、このようなヘッドホンハンガーを用意しておくとデスクの上がすっきり広く使えます。
K&Mの16085というヘッドホンハンガーはデスクの天板や脚、マイクスタンドなど様々な場所に取り付けられます。
ヘッドホンを置く部分をクランプに取り付けるためのネジ穴が3ヵ所あるので、色々なパターンを試しながら快適な位置を決められます。
まとめ
このように音の聞こえ方やヘッドホンの選び方は本当に様々ですが、これがヘッドホン選びの難しさでもあり、面白く奥深いところでもあります。
こういった機材は日頃から目に入るところに置いておくものですので、配信や制作のモチベーションを保つためにも、シンプルに見た目が好みかどうかで選んでしまってもよいかと思います。
筆者
世界にひとつだけのオリジナルの楽器をデザインし、五線譜ではない楽譜やドレミではない音律をグループで話し合って作り、それらを使って音楽をゼロから創作する音楽教育プログラムを中心に、音(楽)にまつわるユニークな取り組みをしています。お仕事のご依頼やコラボレーションのご提案など、お気軽に!
記事をシェアする
関連記事
テーマから探す 検索 人気の記事